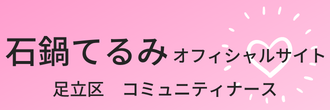コミュニティーナースの石鍋てるみです。
春運動会が行われる学校もあるようで、
時々、練習の音が聞こえます。
足が速い子、長距離が強い子
球技が得意な子、水泳が得意な子など
運動ができると
安心する親御さんも多いでしょう。
一方、その逆だと
心配になってしまいます。
特に親が運動が苦手で、
それをコンプレックスに感じていた場合
我が子にも同じ思いはさせたくないと
習い事で克服させようとする方もいます。
少しくらい泳げないと
体育の授業でかわいそうな思いをすると考えて
スイミング教室に通わせるということもあるでしょう。
そもそも運動が苦手だったり
どこか動きがぎこちなく不器用な
お子さんがいます。

怪我をしやすかったり
無理をしすぎてしまったりして
運動嫌いになってしまう子もいます。
身体を動かす目的は
運動が上手になるためではありません。
健康な身体作りにため、
そして生活していく上で
身体を動かしやすく
機能を最大限に生かすために必要になるのです。
一つの動作、例えば歩くということだけでも
それまでにたくさんの基本となる
発達面での積み重ねが影響し
正しい姿勢で歩けるようになります。
それは、誕生してすぐ
この重力を受ける世界で適応するために
一つ一つ順を追って獲得する課題があって
丁寧にそれを経験し克服することで
正しい歩行動作へとつながるということです。
発達には順番があります。

自分で座ることが出来ないのに
立つことはできません。
ただ、現代は住環境の変化もあるためか
十分なハイハイをしないうちに
つかまり立ち、歩行するお子さんが増えています。
十分なハイハイというのはどのくらい?と
質問を受けることもあるのですが、
それ以前に、赤ちゃんが自由に動くことを
ご家庭で制限していることが気になります。
抱っこ、ベビーカーでの移動も多く
自由に動いていい範囲も半径数メートルに制限され
ベッドで寝かされてばかり
ラックに座らされているなど
とにかく、安全第一とばかりに
自由な動きを束縛されている環境が多いです。
環境が危険から守られすぎて
赤ちゃんが自分で運動機能を
勝ち取る経験が少なすぎる時代です。
発達を段階的に進めていくには
関わる大人が意識して
運動面のサポートが必要となる時代です。
赤ちゃんが誕生してすぐに運動へのサポートは
始まります。
誕生すぐから生後2ヶ月くらいまでには
腹這いで過ごす時間と回数を増やし
1日にトータル20分程度は
腹這いのでの運動を取り入れたいところですが
窒息を心配して安静に寝かせているだけという
親御さんが多いです。
安全に見守りながら進めることが前提ですが
腹這いは骨格系の成長、
運動機能の発達を促すことから
基本となる動作です。

この段階を抜かしてしまうことで
運動の土台ができませんから
以降の積み重ねはうまくいかない
原因になるわけです。
運動面の発達の抜けは
認知の抜けにも影響します。
鉛筆で文字を書く、
ハサミを使うなどの細かい動きを
スムーズに行うための土台が
作られていないという状況になります。
もう、大きくなってしまったから
手遅れだと諦めないでください。
完全なやり直しはできませんが
できることはあります。
身体を使ってたくさん遊ぶ機会を作りましょう。
遊びの中に、ハイハイ
高這いを取り入れてみましょう。
子どもの自由な動きの範囲を妨げず
ちょっと頑張ればできる程度のことを
提示していきます。
レパートリーのある
身体への刺激を与えられるのは
自然の中で遊ぶことが一番です。
決まった遊具、平らに整えられた床、
地面ではなく
複雑な感覚が得られるのは
自然にある物です。
暑くなってくると室内遊びが
増えてしまいがちですが
少しの時間でも外遊びを
取り入れてほしいと思います。