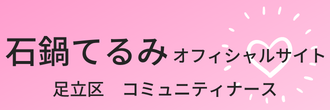コミュニティーナースの石鍋てるみです。
毎日、入れ替わりでいろんなお子さんが
この『一時保育専門託児ルームコミナスキッズ』には
やってきます。
個性たっぷりなので
出会いが楽しみな毎日です。
3歳くらいになると
その個性もはっきり現れ始め
お子さんの自立度、主体性の違いが
目立ってきます。
小さい日常生活の動作や反応に
それは垣間見ることができます。
鼻水が出た時、
自分でティッシュを取りに行って
拭こうとする子もいれば
出しっぱなしで、固まってる子もいます。
「でた〜っ」て教えることはできるけど
誰かが拭いてくれるのを待つだけの子もいます。
お弁当の用意も
不器用なりにも自分で用意しようとする子もいれば
全く自分で蓋も開けようとしないで
待っているだけの子もいます。

その子の理解度や、言葉の発達
器用さなどに配慮しながら
できるだけ、自分でやってみるチャンスを
私たち保育者は奪わないように配慮しています。
あくまでも、保育者はサポートする立場です。
子どもが本当はやれる力を持っているのに
手を貸すということは余計なお世話です。
どこまでができることで
どの部分をサポートすればいいのかは
その時々の子どもの様子で変わりますが
そこを見極められるのが
保育者だと思います。
例えば、ペットボトルを
開けて飲もうとする3歳児を見た時に
初めて開ける時の固くしまった状態は
まだ開けるのは難しい子が多いでしょう。
そんな時、先回りして、大人が開けて
渡すのは、お世話しすぎです。
子どもが手にとって飲もうとした時に
自分で開けられないということを
自覚すること。
そしてその困ったことを
誰かに助けてほしいと訴えられることを
経験するチャンスです。
「開けて〜」あるいは、
そんな動作を訴えてきたら
開けられないということを一緒に確認します。
そして、一緒に最初の力がいる部分を
やってみせます。
ある程度、蓋が緩まれは
子どもが開けるのを見守ります。
そして、自分でできたということを
確認します。

お弁当箱を開ける。
着替えをする。
たくさんの細い日常の動作がありますが
まずは、子ども自身で困ったという経験や
できないということを
できるように見守りましょう。
よく見ればどこを手伝えばいいのかが見えてきます。
つい、見ていられないで手を出してしまったり
失敗してほしくないから
先回りしてしまいがちです。
でも、小さいうちにたくさん失敗を経験することが
大事です。
小さい時ほど、失敗してもケロッとできます。

大事なのは、失敗しても大丈夫、
解決できる方法があることがわかること。
失敗したことを責めたり
叱ったりしないことが関わりでは
大事だと思っています。
小さい子供に固定観念を植え付けることなく
自分の考えで行動する主体性と、
その結果の責任を取る方法を学ぶことが
乳幼児期には大事だと思います。
毎日、いろんなお子さんと接する中で
主体性が育っていないお子さんに
接することもあります。
持っている力を出しきれていないお子さんは
親が関わりすぎてるかな?と
感じることもあります。
短い時間での関わりにはなりますが
その子自身の力を伸ばし
自信につながるようなサポートを
心がけていきたいと思っています。